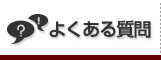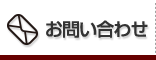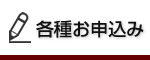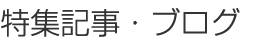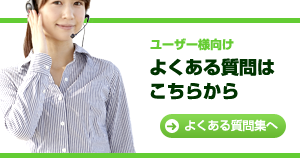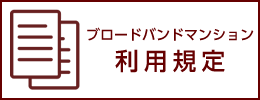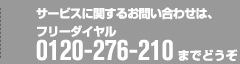雨の日には要注意! 雨の中でのスマートフォン利用|BBM-NET. ビービーエムネット あなたに快適なインターネットサービスを。

-
2025年05月08日
雨の日には要注意! 雨の中でのスマートフォン利用
梅雨の季節になると、突然の雨に見舞われることが増えてきますね。
スマートフォンを使っていて、急に雨に降られたときに、注意することとはなんでしょうか。●まずはスマートフォンの防水性能をチェック
iPhone 13以降やGalaxy S21以降など最近のスマートフォンの多くはIPX7やIPX8などの防水規格に対応していますが、これは「完全に水没させても大丈夫」という意味ではありません。お使いのスマートフォンの防水性能をまず確認しておきましょう。
このIPXは防水に関する機能の高さを示した基準になります。数字が大きいほど防水性能が高くなっています。IPX4:生活防水レベル(雨や汗に耐える)
IPX5:噴流水に耐える(蛇口の水流程度)
IPX6:強い噴流水に耐える
IPX7:一時的な水没に耐える(水深1mで30分まで)
IPX8:継続的な水没に耐える(メーカー指定の条件による、多くは水深1.5m~2mで30分)
注意すべきは、これらのテストは「真水」で行われており、海水や石けん水、プールの塩素水などに対する耐性は保証されていないことです。また、防水機能があっても、日常的に雨の中や水中での使用を想定して設計されているわけではありません。また、経年劣化や落下などで防水性能が低下する可能性もありますので、注意が必要です。●雨の日に役立つ防水対策グッズ
お風呂の中や、雨の中でどうしてもスマフォを使いたい、という場合には以下のようなグッズの活用をおすすめします。・防水ケース・カバー
透明な防水ポーチタイプなら、中に入れたままタッチ操作が可能です。1,000円前後から購入できるものもあり、コスパも良好です。首からかけられるストラップ付きのものを選べば、両手が自由になるメリットもあります。・防水スプレー
スマートフォンケースや布製のカバーに吹きかけることで、撥水効果を持たせることができます。ただし、スマートフォン本体に直接吹きかけるのは避けましょう。・指紋認証・顔認証の代替手段の確認
雨で濡れた指では指紋認証が反応しにくくなります。あらかじめパスコードやパターンなど、代替の解除方法を確認しておくと安心です。顔認証も雨や曇った眼鏡の影響で認識率が下がることがあります。・「グローブモード」の活用
多くのスマートフォンには感度を高めた「グローブモード」があります。これを有効にすると、画面に水滴が付いていても操作しやすくなります。設定アプリの「画面」や「タッチ感度」などから設定できる機種が多いです。・音声アシスタントの活用
「Hey Siri」や「OK Google」などの音声アシスタントを活用すれば、スマートフォンに触れずに操作できます。特に雨の中で地図を見たり、メッセージを送信したりする際に便利です。
イヤホンのボタンで操作
有線・無線を問わず、イヤホンのリモコンボタンを使えば、ポケットや鞄の中にスマートフォンを入れたままでも基本的な操作が可能です。●充電には特に注意
防水性能のあるスマートフォンでもコネクタ部分に関しての防水機能は限定的です。
コネクタ部分やケーブルが濡れた状態でスマートフォンを充電すると、端子がショートして一気に故障することがあります。
スマートフォンによっては充電時に端子が濡れていると「端子が濡れているので充電できません、ケーブルを抜いてください」と警告がでるものもあります。
いずれにしても、端子部分が濡れていると、充電はできませんので「十分に乾いた状態になるまでは充電できない」と覚えておきましょう。
ワイヤレス充電であればコネクタ部分を利用しないので、水濡れに強いですが、ワイヤレス充電器やバッテリーに防水機能が無い場合には充電器側が水に濡れると故障することもあるので注意しましょう。●万が一、水濡れしてしまったら
防水機能のないスマートフォンや、防水性能を超える浸水があった場合の緊急対処法も知っておきましょう。・すぐに電源を切る
水濡れに気づいたら、まず電源を切りましょう。通電状態だと内部回路がショートするリスクが高まります。・拭き取りは丁寧に
やわらかい乾いた布で水分を丁寧に拭き取ります。イヤホンジャックやUSBポートなどの端子部分は特に注意して拭きましょう。端子に水が残っていると、充電時にショートする危険があります。・乾燥させる
最低24時間は自然乾燥させましょう。古典的な方法として、乾燥剤と一緒に密閉容器に入れる方法がありますが、無理に温めたり、ドライヤーを直接当てたりするのは避けてください。熱によって内部部品が損傷する恐れがあります。また、水濡れ後にすぐ充電するのも危険です。完全に乾いてから充電するようにしましょう。
梅雨時期や台風シーズンは、スマートフォンも雨対策が必要です。適切な防水対策を施せば、雨の日でも安心してスマートフォンを活用できます。天気が悪くても、テクノロジーの恩恵を最大限に享受しましょう。